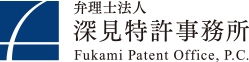当事者系レビューでの特許審判部の決定に基づく二次的禁反言を適用した地方裁判所判決を覆して差し戻した連邦巡回控訴裁判所判決
当事者系レビュー(IPR)において特許審判部(PTAB)が、異議を唱えられた特定の特許クレームは証拠の優越[1]の原則に基づいて特許性がないと決定していました。そのような状況下において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、その後の地方裁判所での訴訟においてその特許の他の未審査のクレームについて特許権者が侵害を主張することを、二次的禁反言として妨げられることはないと認定しました。
Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc., Case No. 23-1359 (Fed. Cir. February10, 2025) (Prost, Reyna, Taranto JJ.)
1.事件の経緯
(1)特許侵害訴訟の提起
Kroy IP Holdings, LLC(以下「Kroy社」)は、コンピュータネットワーク上でのインセンティブプログラム[2]の提供に関連する米国特許第6,061,660号(以下「’660特許」)を所有しています。
Kroy社は2017年10月に、’660特許の13のクレームを侵害したとして、デラウェア州連邦地方裁判所(以下「地裁」)にGroupon, Inc.(以下「Groupon社」)を提訴しました。
(2)当事者系レビュー(IPR)の請願
それに対してGroupon社は、2018年10月に、’660特許の21のクレームに異議を唱える2つのIPRの請願書を提出しました。
(3)訴状の修正(1回目)
Groupon社のIPR請願期限が過ぎた後、Kroy社は訴状を修正し、’660特許から、訴訟対象のクレームを追加しました。追加されたクレームの多くは、Groupon社のIPR請願の対象には含まれていませんでした。
(4)IPRにおける審判部の決定と、それに対するCAFCへの控訴
IPRにおいてPTABは、2020年4月に、‘660特許の異議を申し立てられた21のクレームすべてについて特許性がないと判断しました。それに対してKroy社は、最終的なPTABの決定に対して控訴しましたが、CAFCはPTABの決定を支持しました。
(5)訴状の修正(2回目)
Kroy社は2022年3月に2回目の訴状の修正を行ない、今回は、IPRで特許性がないとされた21のクレームを訴訟対象から削除し、IPRにおいて特許性が争われなかった14のクレームを新たに訴訟対象として、Groupon社の特許侵害を主張しました。
(6)Groupon社による、訴訟却下の動議と、地裁の判断
Kroy社の2回目の訴状の修正に対して、Groupon社は、二次的禁反言の原則[3]に基づいて、特許性のないクレームに関するPTABの以前のIPRの決定により、Kroy社による新たなクレームに基づく侵害の主張は阻止されると主張し、訴状却下の動議を地裁に提出しました。
地裁はこれに同意し、PTABが特許性がないと判断したクレームとその他のクレームとが実質的に相違しないという最終判断を下した場合、二次的禁反言は当該その他のクレームを無効にするために適用されると認定しました。
この認定に際して地裁は、まず、2018年のXY, LLC v. Trans Ova Genetics, L.C.事件CAFC判決(以下「XY判決」)[4]を引用して、特許クレームの特許性に関する審判部の最終決定は、同じクレームに係る係属中の地裁の訴訟において同じ判断をもたらす効力を有する判断しました。次に、地裁は、2013年のOhio Willow Wood Co. v. Alps S., LLC事件CAFC判決(以下「Ohio Willow Wood判決」)を引用して、未審理のクレームと審理済みのクレームとの相違が特許無効の判断を実質的に変更しない場合、以前に審理されていない特許クレームに二次的禁反言が適用される可能性があると判断しました。
これら2つの判決を総合して、地裁は、新たなクレームは無効性の点で、IPRにおいて特許性がないとされたクレームと実質的に相違しないと判断し、2022年12月に、Groupon社が提出した訴訟却下の動議を認める判決を下しました。
それに対してKroy社はCAFCに控訴しました。
2.CAFCにおける審理
(1)本件の争点と当事者の主張
CAFCはまず、本件の争点が、「PTABが特許性がないと最終的に決定した特許クレームと、同じ特許から抽出した他のクレームとが、無効性の観点から実質的に相違しないと仮定した場合に、PTABの事前の最終決定が、特許権者が当該他のクレームに基づいて改めて権利主張することを妨げるかどうか」という点にあることは明確であると指摘しました。
この点に関してKroy社は、特許クレームの無効性についての地方裁判所における立証責任よりも、特許クレームが特許性がないことを証明するためのIPR手続における立証責任の方が軽いため、本件には二次的禁反言は適用されるべきではないと主張しました。
それに対してGroupon社は、上述のXY判決およびOhio Willow Wood判決に基づいて、二次的禁反言が適用されると反論しました。
(2)CAFCの判断
CAFCは、上記Kroy社の主張に同意して、本件には二次的禁反言は適用されないと判断しました。その理由は以下のとおりです。
(a)二次的禁反言が適用されるための要件とその例外
過去のCAFCの判決(たとえばJean Alexander Cosmetics, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 458 F.3d 244, 249 (3d Cir. 2006))[5]に基づき、二次的禁反言は、原則として次の4つの要件が満たされる場合に適用されます。
(i)後の手続きと同一の論点が先の手続きで決定されたこと、
(ii)当該論点が先の手続きで実際に争われたこと、
(iii)当該論点の決定が先の手続きにおける最終決定に不可欠であったこと、および
(iv)後の手続きの当事者が先の手続きの当事者と同一であり、当事者は先の手続きにおいて当該論点を争う十分かつ公正な機会が与えられていたこと。
ただし、二次的禁反言には例外があります。
例外の1つは、「後の手続き(訴訟)が、異なる立証責任など、異なる法的基準の適用を伴う場合」です。例えば、「証拠の優越の原則の下で下された先行判決は、明確で説得力のある証拠基準[6]の下で訴訟されたその後の問題において二次的禁反言効果を与えることはできない」と説明している判決[7]があります。また、「証拠の優越によって争点を立証する責任を負った当事者は、より高い基準による同じ争点の証明を必要とする後の訴訟において排除を主張する権利はない」と述べた文献[8]もあります。
(b)過去のCAFC判決に基づく考察
CAFCは、最近の2024年のParkerVision v. Qualcomm事件CAFC判決(以下「ParkerVision判決」)[9]を引用して、まだ有効性が判断されていない新たな訴訟対象クレームには二次的禁反言は適用されないことを明確に示しました。ParkerVision判決においてCAFCは、IPR手続において請願人は、証拠の優越の原則により特許性がないことを証明する責任を有するものの、無効性について明確で説得力のある証拠のより高い負担を、地裁が要求していると認定していました。
このようなParkerVision判決に基づく考察によりCAFCは、本件訴訟においても、Groupon社が明確で説得力のある証拠によって、地裁でこれらの新たな請求の無効性を証明すべきであったと説明しました。
Groupon社が2013年のOhio Willow Wood判決に依拠したことについてCAFCは、Ohio Willow Wood判決の禁反言のシナリオは、特許クレームの無効性に関する同じ立証責任を含む地裁の裁判で発生たものであって、本件の場合のように、PTABが証拠の優越の原則に基づいて、特定の特許クレームについて特許性がないと判断し、その他のクレームについては、PTABの判断を経ていないため、地裁の訴訟において特許権者が他の有効性を判断されていない特許クレームを主張することは、二次的禁反言により差し止めることはできないと指摘しました。
(c)CAFCの判決
上記考察に基づく結論としてCAFCは、Groupon社の申立てを却下し、Kroy社の主張に同意して、訴訟を地裁に差し戻す判決を下しました。
3.実務上の留意点
本件判決の判示内容から、特許侵害訴訟の当事者は、以下の点に留意すべきことが示唆さます。
特許侵害訴訟の当事者は、同じ特許に関する以前の行政手続きや訴訟での決定に基づく二次的禁反言の適否が問題になった場合、本件判決で明記された二次的禁反言の4つの要件とその例外について十分理解した上で対処する必要があります。
本件のような状況、すなわち、IPRで特定のクレームについてPTABにより特許無効の決定を受けた特許に基づいて、特許権者が、その特許の当該特定のクレーム以外の新たなクレームに基づいて特許権侵害を主張する場合、特許権者としては、新たなクレームの有効性について二次的禁反言が適用されて新たなクレームが無効にされることを回避するため、二次的禁反言適用の例外として、例えば以下の点を主張する必要があります。
(i)PTABの審理における証拠の優越に基づく立証責任に比べて、裁判所の審理における立証責任の負担がより大きいこと。
(ii)あるいは、特許の有効性に関する判断内容が、PTABが無効であると決定したクレームと、侵害訴訟において侵害を主張するクレームとで実質的に相違すること。
同じ状況下において被疑侵害者の立場からは、二次的禁反言の適用を主張する観点から、特許侵害を主張された新たなクレームについての有効性の判断が、IPRでPTABが特定のクレームについて無効と決定した理由と実質的に相違しないことを主張することが有効であると言えます。
[情報元]
1.IP UPDATE (McDermott) “Collateral Estoppel Doesn’t Apply to Unchallenged IPR Claims”February 20, 2025
https://www.ipupdate.com/2025/02/collateral-estoppel-doesnt-apply-to-unchallenged-ipr-claims/
2.Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.事件判決原文
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1359.OPINION.2-10-2025_2465811.pdf
[担当]深見特許事務所 野田 久登
[1] 米国における証拠の優越(Preponderance of evidence)とは、民事訴訟で物事を立証する際に要求される立証の程度(standard of proof)の一つであって、ある事実が“ないというよりはある(more likely than not)”と言えるかどうかで判断する原則を言います。
[2] インセンティブプログラム:販売促進やブランド力向上等を目的としてに、顧客等に、ポイント制度や割引クーポンのような種々の形態で報酬や特典を提供するプログラム
[3] 二次的禁反言(collateral estoppel)の原則とは、米国訴訟において採用されている衡平法上の原則であって、同一当事者間の先の訴訟で十分かつ公正に審理され、かつ一方の当事者にとって不利であるように判断された争点については、他方の当事者は、後の事件においては争わなくても済むように保護する原則を言います。詳細は、弊所ホームページ「国・地域別IP情報」において2023年7月25日付で配信した、「地裁で無効とされたクレームに対するIPRの開始の是非に関するUSPTO長官の職権レビュー」と題したの記事(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/9725/)をご参照下さい。
[4] https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1934402.html
[5] https://caselaw.findlaw.com/court/us-3rd-circuit/1347951.html
[6] 明確で説得力のある証拠基準(a clear and convincing evidence standard):民事訴訟の原則である証拠の優越の原則よりも高いが刑事訴訟の証明度よりは低い証明度
[7] Grogan v. Garner, 498 U.S. 279, 284–85 (1991)
[8] Charles Alan Wright, Arthur R. Miller & Edward H. Cooper, Federal Practice & Procedure § 4422 (3d ed. 2016)
[9] https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1755.OPINION.9-6-2024_2380516.pdf