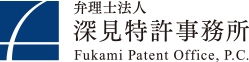UPC協定の非締約国で有効化された欧州特許に関する侵害訴訟についてUPCが裁判管轄権を有すると判示したUPCデュッセルドルフ地方部判決
1.事件の概要
統一特許裁判所(UPC)は、UPC協定の発効によりUPC協定締約国に共通の単一の特許裁判所として創設されました。UPC協定によりますと、UPCの判決の効力は、欧州特許が有効化されているUPC協定締約国の領土をカバーします(UPC協定第34条[i])。
この度、UPCのデュッセルドルフ地方部は、UPC協定締約国全体とそれを超えた地域にまで波紋を呼ぶ判決を下しました(UPC事件番号:UPC_CFI_355/2023、判決日:2025年1月28日)。
この判決においてデュッセルドルフ地方部は、UPC協定の非締約国(イギリス[ii])で有効化された欧州特許に関する侵害訴訟を審理する管轄権をUPCが有すると判示しました。以下に、この判決の詳細について検討し、その潜在的な影響について考察します。
2.事件の経緯
(1)訴訟の提起
Fujifilm Corporation(以下、「富士フイルム」)は、オフセット印刷技術に関する自社の複数の欧州特許を侵害したとして、Kodakのグループ企業3社(以下、総称して「コダック」)をUPCの別々の地方部に訴えました。具体的には、富士フイルムは、2件の侵害訴訟をUPCのマンハイム地方部に提起するとともに、3件目の侵害訴訟をUPCのデュッセルドルフ地方部に提起しました(この3件目の侵害訴訟を以下「本件訴訟」と称します)。これらの訴訟の当事者全員がドイツに住所を有していました。
コダック社は、本件訴訟の提起に応答して、特許取消の反訴をデュッセルドルフ地方部に起こしました。デュッセルドルフ地方部は特許取消の反訴も併せて審理することになりました。
(2)対象特許
本件訴訟の対象となったのは、富士フイルムの欧州特許EP3594009(以下、「本件欧州特許」)であり、本件欧州特許は、ドイツおよびイギリスの2ヶ国で有効化されています。
(3)原告の請求
原告である富士フイルムは、訴状において、UPC協定締約国であるドイツに加えて、UPC協定非締約国であるイギリスにおける、被告コダックによる侵害行為の差し止を求めました。
2.デュッセルドルフ地方部の判断
(1)UPC協定非締約国での裁判管轄権に関する当事者の主張
富士フイルムとコダックはともに、本件欧州特許のイギリス部分に関するUPCの管轄権について意見を提出しました。
富士フイルムは、訴訟当事者全員がドイツに住所を有しているという理由で、UPCは本件欧州特許のドイツ部分およびイギリス部分の両方に対して管轄権を有すると主張しました。富士フイルムはまた、デュッセルドルフ地方部は、イギリスがまだ欧州連合(EU)加盟国であったブレグジット移行期間の終了日(2021年12月)までの間に行われた侵害行為を少なくとも検討すべきであると主張しました。
コダックは、イギリスはUPC協定の締約国ではないため、イギリスに関連する限りにおいては、UPCは欧州特許に対する管轄権を有しないと反論しました。コダックの主張によれば、UPCの判決の効力が及ぶ地域的範囲は、EU加盟国ではなくUPC協定締約国でもないイギリスにまで拡大することはできません。
(2)UPC協定非締約国での裁判管轄権に関するデュッセルドルフ地方部の見解
① 取消訴訟について
デュッセルドルフ地方部は本件訴訟の判決で、富士フイルムによる本件欧州特許の訂正要求を却下し、本件欧州特許は欧州特許条約(EPC)に基づき無効であると認定しました。デュッセルドルフ地方部は、本件欧州特許のドイツ部分を取り消しましたが、現在も有効に存続しているイギリス部分を取り消す権限がUPCにはないことを認めました。
デュッセルドルフ地方部は、UPCには本件欧州特許のイギリス部分を取り消す権限はないものの、無効理由自体はイギリス部分にも適用され得るであろう、と判示しました(イギリス国内では本件欧州特許のイギリス部分に対する取消訴訟は提起されていませんでした)。
② 侵害訴訟について
デュッセルドルフ地方部は、上記の取消訴訟とは異なり、UPCには本件欧州特許のイギリス部分の侵害を判断する権限があり、したがってイギリスで行われた侵害行為に関して救済措置を適用する権限がある、と判断しました。一般に、係争中の特許を取り消せば、侵害についてはもはや検討する必要がなくなるであろうと考えられますが、本件訴訟においてデュッセルドルフ地方部は、本件欧州特許を無効と判断しつつも、UPC協定の非締約国における侵害行為に関してがUPCが審理しその判決を執行する管轄権を有するかどうかについての法的分析を行いました。
その結果、権利の侵害/執行の問題に関する決定に関して、デュッセルドルフ地方部は富士フイルムの側に立って、イギリスに関して管轄権がないとのコダックの主張を否定しました。実際、デュッセルドルフ地方部は、UPC協定の関連条項は、UPC協定締約国の領域外に影響を及ぼす決定を排除するものではないと判断しました。その根拠についてデュッセルドルフ地方部は、国際裁判管轄権に関するUPC協定第31条[iii]によって準用されるブリュッセルIbis規則(Regulation(EU)No 1215/2012)に依拠して、被告が締約国(ドイツ)に住所を有している場合、被告はその締約国の裁判所で訴えられるべきであるとの判断を下しました。ブリュッセルIbis規則(Regulation(EU)No 1215/2012)とは、EUにおける裁判管轄権の枠組み、すなわちどのEU加盟国の裁判所が、複数のEU加盟国に関係する訴訟で管轄権があるかどうかを判断するために使用する規則であり、その基本原則は、被告当事者のEU加盟国の裁判所が管轄権を持つというものです[iv]。
デュッセルドルフ地方部は、Regulation(EU)No 1215/2012の第4条第1項[v]の規定(以下、「本規定」)に基づき、締約国に住所を有する者は、国籍に関係なく、その締約国で訴訟を起こされることになるものであり、本件訴訟においては被告は全員ドイツに住所を有していること、欧州連合司法裁判所(ECJ)が本規定の適用に必要な国際的要件がEUの域内のみに限らないことを認めていること、を指摘しています。そして、本規定に基づき、被告の居住国である加盟国の裁判所の管轄権は普遍的であり、欧州特許が有効化されているすべての国における特許侵害に適用される可能性があることを示しています。
このようにデュッセルドルフ地方部は、侵害訴訟の目的上、UPCはUPC協定締約国の裁判所であると結論付けました。重要なのは、デュッセルドルフ地方部が、この管轄権は、イギリスなどの非EU加盟国であるEPC加盟国に関する侵害訴訟にも及ぶと判断したことです。一方、これらの欧州特許が有効ではなく効力を持たない、米国や中国などの他の第三国にはUPCの管轄権は及ばないと判断されました。
3.UPCの管轄権の法的概念
UPCの管轄権が、UPC協定の締約国ではないEPC加盟国にどの程度まで拡大できるかという「ロングアーム(遠くまで及ぶ)管轄権(long arm jurisdiction)」という法的概念は、UPC協定が発効するずっと前から議論されていました。UPC協定非締約国での侵害行為に対する裁判管轄をUPCが有する条件は、当該UPC協定非締約国において欧州特許が有効であり、かつ侵害当事者自身がUPC協定の締結国に住所を有していることだけのようです。
これらの要件は、最近のフランス最高裁判所の判決(21-11.085)とほぼ同様であり、この判決において、原告と被告の一部がフランスに拠点を置いている場合、フランスの裁判所はフランス国境を越えた特許侵害問題を裁定する管轄権を有する、と判断されました。
さらに、同様の疑問、すなわち、「UPCの管轄権が、UPC協定の締約国ではないEPC加盟国にどの程度まで拡大できるか」という疑問が、ECJで係争中のBSH/Electrolux事件(C-339/22)の根拠となっています。この訴訟では、ブリュッセルIbis規則は、EUの領域外で有効な欧州特許に関する侵害訴訟を裁判所が審理するのに十分な根拠を提供するという法務長官の意見が示されています。
一方でUPC控訴裁判所は、最近のAbbott v SiBio事件(UPC_CoA_388/2024)で、第一審裁判所のUPC管轄権拡大の希望を却下しました。この判決で、UPC控訴裁判所は、UPCの管轄権はUPC協定を批准していない国には及ばないことを迅速かつ断固として明確にしました。このことから本件訴訟がUPC控訴裁判所に控訴された場合に、控訴裁判所がデュッセルドルフ地方部の判決を支持するのかどうかを予測することは今のところ難しいように思われます。
4.戦略的な検討
本件訴訟の第一審(デュッセルドルフ地方部)判決が控訴され、上記のフランス最高裁判所判決(21-11.085)やECJで係争中のBSH/Electrolux事件(C-339/22)を考慮して、UPCの控訴裁判所が第一審判決を支持した場合、当事者は、欧州特許を侵害する行為に関して、問題となっている国がUPCの締約国であるかどうかに関係なく、単一の裁判所であるUPCに侵害訴訟を提起し、包括的な救済を得ることができる可能性があります。EPCのすべての加盟国がUPCの締約国になっているわけではないため、特に2021年にUPC協定から脱退したイギリス、UPCの締約国ではないスペインやポーランドについて、ロングアーム管轄権は興味深い問題です。これにより、これまでは自身の従来型の欧州特許をUPC協定からオプトアウトしてきたような当事者にとっても、UPCの魅力が増すことになり得ます。
判決がUPCの控訴裁判所によって支持された場合、欧州特許の付与時に、イギリス、スイス、スペイン、ポーランド、クロアチア、トルコなど、EPC加盟国であるがUPC協定締約国ではない地域の指定を検討することが重要になる可能性があります。侵害訴訟はEU加盟国に住所を有する被告に対して開始される可能性がありますが、この判決から、救済策の取得は、今回のイギリスのように、並行して有効性に関する国内の訴訟手続きがなされていないEU加盟国に限定される可能性があることがわかります。
この判決と、UPC協定非締約国で行われた行為に基づく侵害訴訟の潜在的な増加とを考慮すると、各国の国内特許庁と国内裁判所が、それぞれの管轄権が侵害されていることが明らかな状況で、ロングアーム管轄権の問題にどのように対応するかは興味深いことです。特に、国家主権への影響を考慮すると、UPCの「ロングアーム管轄権」の脅威とみなされるものに対して、各国の国内裁判所または政府が積極的に対抗しようとするかどうかは興味深いことです。
興味深いことに、デュッセルドルフ地方部の判決は、UPC協定非締約国における特許に関する侵害訴訟および取消訴訟が、UPCとUPC協定非加盟国の国内裁判所との間で二分される可能性があるという潜在的なシナリオも設定しています。デュッセルドルフ地方部が、訴訟の対象となっているイギリス特許はイギリスでも有効性がないだろうと指摘したことは興味深いことですが、特に本件訴訟において適用された基準が、関連する国内法(イギリス特許法)ではなくEPCの基準であったことを考えると、イギリスにおいても有効性がないという結論は決して保証されたわけではありません。最初から慎重に検討しなければ、UPCに侵害訴訟を提起した訴訟当事者にとって、訴訟結果の内容の低下をもたらす可能性があります。実際、この点での反競争的行為に伴うリスクは、有害な結果をもたらす可能性があります。
富士フイルムまたはコダックがデュッセルドルフ地方部の判決に対して控訴するかどうかはまだわかりません。それでも、ECJのC-339/22の判決は、他の管轄区域で有効な欧州特許に関してUPCおよびその他の国内裁判所がどのように行動するかを再形成する上で役立つ可能性があるようです。言うまでもなく、その影響は法的確実性の観点からだけでなく、政治的観点からも重大です。
[情報元]
情報元①
D Young & Co Patent Newsletter No.105 February 2025 “UPC crosses borders and breaks boundaries: long arm jurisdiction questions arise again!”
(https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-long-arm-jurisdiction-fujifilm-kodak)
情報元②
Decision of the Court of First Instance of the Unified Patent Court delivered on 28 January 2025
concerning EP 3 594 009 B1(UPCデュッセルドルフ地方部判決原文)
[担当]深見特許事務所 堀井 豊
[i] UPC協定第34条(Territorial scope of decisions)は以下のように規定しています。
“Decisions of the Court shall cover, in the case of a European patent, the territory of those Contracting Member States for which the European patent has effect.”
[ii] イギリスはEUからの離脱(ブレグジット)により、EU加盟国であることを参加要件とするUPC協定から2021年に離脱しました。
[iii] UPC協定第31条(International jurisdiction)は以下のように規定しています。
“The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention).”
[iv] Regulation – 1215/2012 – EN – Brussels I bis – EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj/eng)を参照
[v] Regulation(EU)No 1215/2012の第4条第1項は以下のように規定しています。
“Subject to this regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the court of that Member State.”